赤色3号(エリスロシン)は、医薬品や食品の添加物として世界中で利用されています。
しかしながら、米国において、2025年1月15日、FDAが医薬品(内服用)や食品での赤色3号の使用を禁止する旨を公表しました(FDAのウェブサイト)。
このような状況を受けて、日本でも医薬品(内服用)や食品での赤色3号の使用に関する対応が整理されてきましたので、まとめておきます。
日本における医薬品(内服用)での赤色3号(エリスロシン)の今後の使用
2025年4月18日付けで厚労省が「赤色3号を含有する内用医薬品等に関する自主点検について」という通知を発出しました。
この通知に基づき、内服用医薬品(及び医薬部外品)の製造販売業者は、以下の対応が求められます:
- 各医薬品における赤色3号の使用量を確認するとともに、承認された用法・用量を踏まえ、一日最大摂取量を算出する
- 一日最大摂取量が、一日許容摂取量(0.1mg/kg体重/日)を上回る医薬品について、2025年5月16日までに厚生労働省医薬局医薬安全対策課に報告する
- その医薬品における赤色3号の使用量の変更等の対応の要否について検討し、最初の報告から1か月以内に、厚生労働省医薬局医薬安全対策課に相談する
上記通知発出及び対応は、2025年3月25日に開催された令和6年度第11回薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会での審議結果に基づくものです。
安全対策調査会で示された対応方針は、FDAの措置に至った根拠情報には新たな知見はないこと、ラット試験での甲状腺の発がんが認められた用量は医薬品の服用で人が摂取する量と比べて極めて高用量であることを踏まえて、赤色3号の使用を禁止する必要はないというものでした。(食品での対応状況も踏まえています。)
一方で、業界自主アンケート調査の結果から、一部の医薬品で許容一日摂取量(ADI)を超える量の赤色3号を含有することが確認されたとして、製造販売業者に対し、赤色3号の含有量の自主点検を求めることともされました。
なお、赤色3号に対する国立医薬品食品衛生研究所の見解は以下です:
- ラットの甲状腺ホルモンの T4 から T3(活性型)への変換を阻害する作用があることが報告されている
- したがって、下垂体からの長期的な甲状腺刺激ホルモン(TSH)刺激による発がんメカニズムが考えられる
- T4からT3(活性型)の変換阻害は人でも起こりうる可能性があるが、甲状腺ホルモンと TSH の動態は人とラットでは種差があることが知られている
- 動物試験のように高濃度、高用量で人で赤色3号が摂取される可能性は想定できない
- 以上から、赤色3号についてラット試験で認められた甲状腺での発がんについては、人では安全性上問題とならないと考えられる
米国の対応
米国では2028年1月18日までに内服用医薬品での赤色3号の使用をやめる必要があります。FDAのこの判断は、2022年に提出された請願に基づくものであり、ラットでの発がん性を示唆した試験データを評価した結果の対応となっています。
その他
食品については、「現時点で直ちに「食用赤色3号」の指定を取り消す又は使用基準を改正する必要はない」との判断になっています(関連資料)。
この判断は、毒性や発がん性の評価に加えて、現在の国内での推定摂取量は国際機関が設定した許容一日摂取量(ADI)を大幅に下回っているためとされています。
したがって、日本では、引き続き、食品に対しても赤色3号が使用されることとなります。

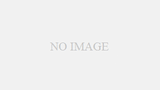
コメント